19世紀の画家ジャン・ベローの絵画に登場するパリジェンヌのファッションを楽しみましょう。

『過ちのあとで』( Après la faute ) 1885年-1890年頃 ジャン・ベロー ナショナル・ギャラリー蔵

引用元:『過ちのあとで』
何故泣いているんだろう。
何を泣いているんだろう。
外套も脱がずに。
と、まず思いませんか。
題は『過ちのあとで』です。
ということは、彼女は何か大きな過ちを犯して泣いているのでしょうか。
瀟洒で上等な衣装を身に着けた若い女性がいるのは、
たぶん、自宅の客間ではない。温かそうな毛皮の襟巻を着けているからだ。彼女は顔を覆い、豪勢なソファの肘掛けのところに身を寄せている。ベローのタイトル ― 《過ちのあとで》 ― が話の残りを語っており、見る者の注意をしわの寄ったビロードのクッションに引き付ける。そこには、この婦人の誘惑者が座っていた痕跡が残っている。
エリカ・ラングミュア(著).高橋裕子(訳).2005-25.『物語画』.八坂書房. p.120.
隣に座っていたのは誰だったのですか?
「彼」はどうして席を立ってしまったのでしょう?
私たち鑑賞者は、美しいであろう彼女の容貌に、あるいは彼女の犯した罪の種類に、様々に想像を巡らせます。
ベローはそれ以上を答えようとはしていません。
『過ちのあとで』はエリカ・ラングミュア氏の著書『物語画』に掲載されています。翻訳は『イギリス美術』(岩波新書)の高橋裕子氏。
パリジェンヌたち
フランスの画家ジャン・ベロー( Jean Béraud, 1849年1月12日-1935年10月4日)は、パリの都市や人々の生活を多く描きました。
パリジェンヌ、カフェ、シャンゼリゼ、コンコルド広場などのタイトルに胸が躍ります。
Parisienne au Bois 1890年 ジャン・ベロー カルナヴァレ美術館蔵
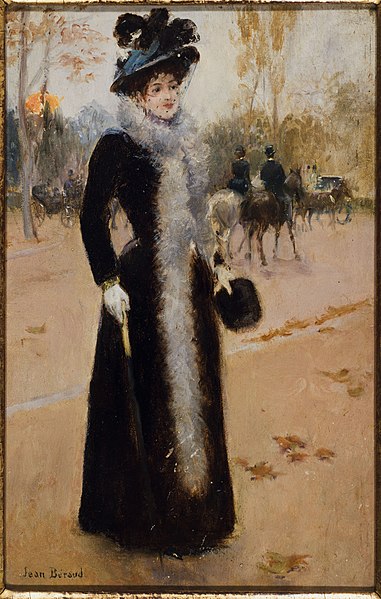
邦題を付けるとしたら、『森のパリジェンヌ』?
温かそうな襟巻ですね。
『過ちのあとで』の女性がしているものも長い襟巻ですが、こちらの女性たちのものも長さがありますね。1880年代後半にはこんな長さの襟巻が流行ったのでしょうか。
襟巻に対する言及はありませんでしたが、パリジェンヌたちの着ている服の色については、
パリの街をスナップ写真のように切り取るジャン・ベローの画面には、すでに黒服が定着していた男性は別として、女性の多くが黒い服で登場している。
深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.123.
黒=喪服ではなく「シック」ですね。
『コンコルド広場のパリジェンヌ』( Parisienne sur la place de la Concorde ) 1885年頃 ジャン・ベロー カルナヴァレ美術館蔵

引用元:『コンコルド広場のパリジェンヌ』
カルナヴァレ美術館:Parisienne sur la place de la Concorde
お届け物?
『通りを渡る婦人』( Jeune femme traversant le boulevard ) 1897年 ジャン・ベロー 個人蔵
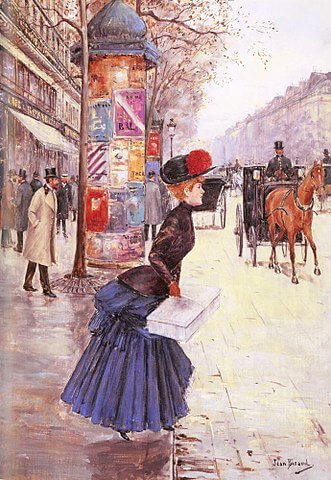
A Windy Day on the Pont des Arts 1880年-1881年 ジャン・ベロー メトロポリタン美術館蔵

引用元:A Windy Day on the Pont des Arts
メトロポリタン美術館:A Windy Day on the Pont des Arts
「ポンデザール」(アール橋)の上の、風の強い日。
寒い季節に咲く、パリジェンヌの胸の花飾りがステキ。
帽子箱を運ぶ女性たち
1800年代後半、パリの洋服店や帽子店には「トロタン」と呼ばれる使い走りの若い女性がいました。
トロタンは、客が注文した品を屋敷まで届けてくれます。
帽子は男女とともに当時の身支度には必需品で、女性の帽子には、ドガがたびたび描いた帽子店の様子でわかるように、羽根やら造花やらさまざまな飾りがついていた。そのために帽子箱は軽くても思いのほか大きい。似たような帽子箱を持ったお使いの女性は、パリの街頭風景を描いたベローも《パリ、アーヴル通り》などでたびたび登場させている。
深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.125.
『パリ、アーヴル通り』( Paris, rue du Havre ) 1881年 ジャン・ベロー ワシントン、ナショナル・ギャラリー蔵
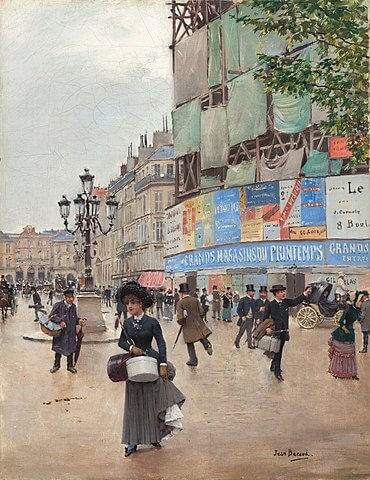
引用元:『パリ、アーヴル通り』
ナショナル・ギャラリー・オブ・アート:Paris, rue du Havre, c. 1882
冬の街に、カラフルな広告が楽しいですね。
彼女が手にしている複数の箱はお客様への届け物なのでしょう。
『シャンゼリゼの帽子屋』( La Modiste Sur Les Champs Elysées ) 1880年代 ジャン・ベロー 個人蔵
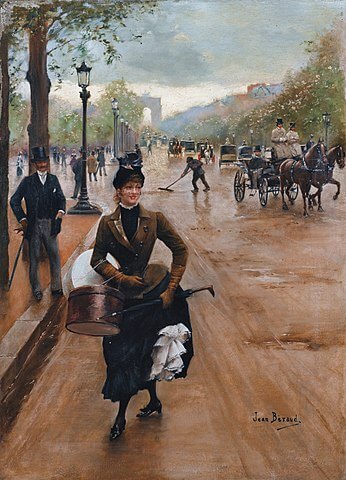
引用元:『シャンゼリゼの帽子屋』
上の絵は、『ヨーロッパ服飾史』(河出書房新社)では『シャンゼリゼのモディスト』として掲載されています。
裾をたくし上げている女性は、箱を持っているから、客に商品を届けるモディストである。背後に男の姿がある。女性像に男の姿やその視線を添える風俗画は世紀末のパリに多い。
徳井淑子(著). 2015-10-30. 『ヨーロッパ服飾史』. 河出書房新社. p.94.
modiste モディストは、「仕立て屋、帽子屋、仕立屋、お針子、ドレスメーカー」(DICTIONARY / 英ナビ!辞書)です。
ベローは他にも「トロタン」と思われる女性の姿を描いています。
Le boulevard des Capucines et le théâtre du Vaudeville 1889年 ジャン・ベロー 個人蔵
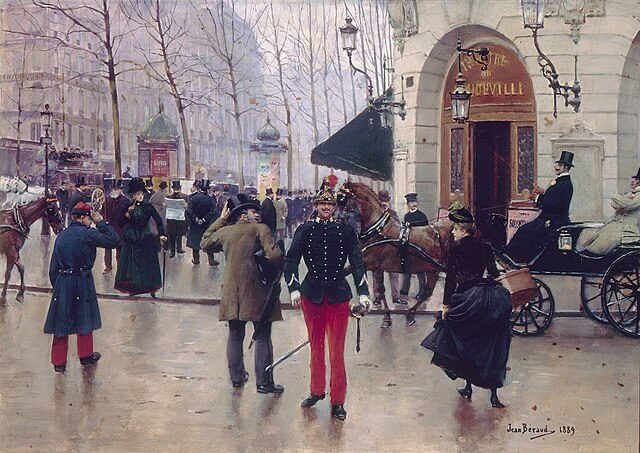
引用元:Le boulevard des Capucines et le théâtre du Vaudeville
”Le boulevard des Capucines et le théâtre du Vaudeville” 「キャピュシーヌ大通りとヴォードヴィル座」(カピュシーヌ大通り?) でいいのかな??フランス語、忘れました。すみません。
Modiste sur le Pont des Arts 1880年頃 ジャン・ベロー 個人蔵

引用元:Modiste sur le Pont des Arts
こちらもアール橋の上の風景、ポン・デ・ザールの上のモディスト、というタイトルですね。
絵画の中は寒い季節ですが、冬枯れのパリもやっぱり素敵ですよね。
- エリカ・ラングミュア(著). 高橋裕子(訳). 2005-5-25.『物語画』. 八坂書房.
- 深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書.
- 徳井淑子(著). 2015-10-30. 『ヨーロッパ服飾史』. 河出書房新社.

コメント